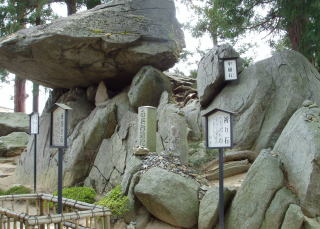|
 |
| 老木の根元は逞しい |
 |
| ヒメシャガの花 |
 |
| 旧道には僅かに松並木の面影を残すところが・・・ |
|
桜前線は北上まっ盛りである。
「奥の細道」の続きは、桜の見ごろにと思っていたこともあり、ようやく4月の末になって五ヶ月ぶりの再開となった。
この地方の桜の開花は、東京よりおよそ一ヶ月は遅い。
根尾谷の薄墨桜(岐阜)・山高の神代桜(山梨)と共に日本三大桜と並び称される「三春の滝桜」は、満開をすこし過ぎようかという頃である。こうして毎年見事な花を咲かせ続ける老樹は、樹齢千年とも云われて、地元の人たちの日ごろの管理もさぞや大変なことに違いない。
滝桜見物には任意だが協力金が要る。寄付金は古木の維持管理に使われるという。気の遠くなるほどの時間を、堂々と生き続けた逞しい大木を前にしてみると、駐車代500円・協力金500円なりも、至極当然なことだと納得させられる。
見事に咲き誇る桜を眺める前方から、『 こんにちは!、コンニチハ!』と、やけに愛想の良い女性二人がこちらへ向って歩いて来た。一行はテレビの旅番組のロケのようで、愛嬌を振りまく「木の実ナナ」とは対照的に「富士真奈美」の方は随分と無口で静かな人のように見えてしまう。こういうものはもっとじっくり撮影するのかと思っていたのだが実際は違っていた。滝桜の前でカメラを廻していたのは、ほんの10分程度である。撮り終えた一行は、長居は無用とばかりにそゝくさと立ち去った。
ゴ−ルデンウイ−クも終わりの日曜の夜のこと。全くの偶然だが、テレビでこの時の映像をチラリと目にした。次週の番組の予告で、どうやら次の日曜日にこれが放送されるようだ。だが、その日は生憎と、一泊の遠出をする予定になっている。まァあの程度のロケではほんのワンシ−ンだけで、楽しみにするほでもないような気もするのだが・・・・。
芭蕉は郡山で、ひとつの花をさがしている。昔から多くの和歌に詠み込まれた「花かつみ」である。しかし芭蕉が訪れたときに、辺りに花かつみを知るひとはいない。
しかし、郡山ではヒメシャガを「花かつみ」とよんで、市の花に決めている。花の色には、白と紫があるそうだ。 |